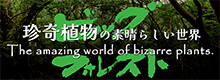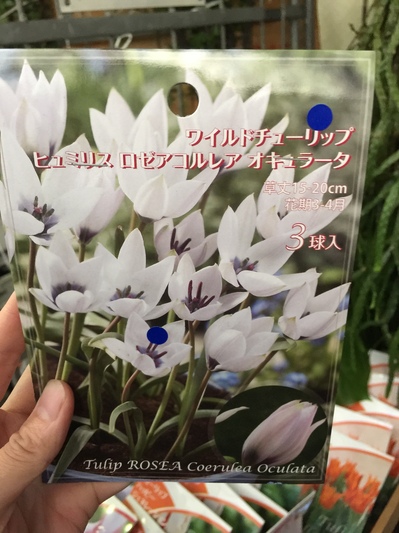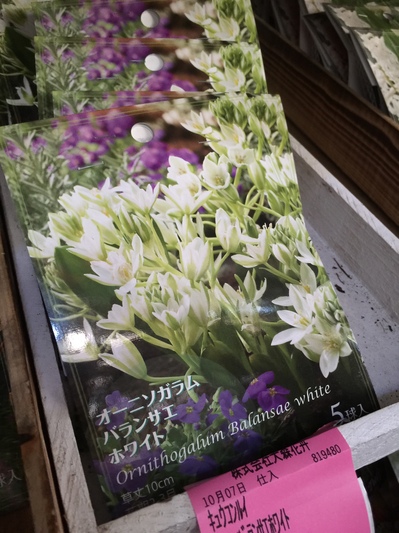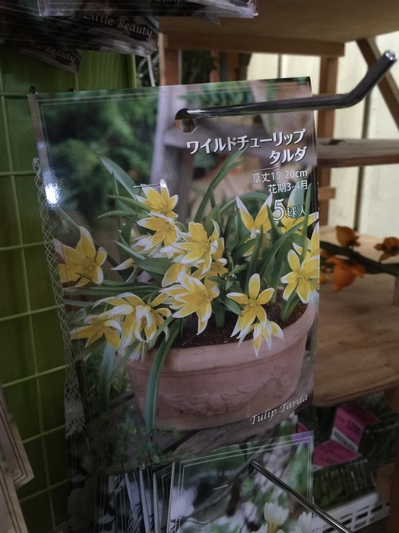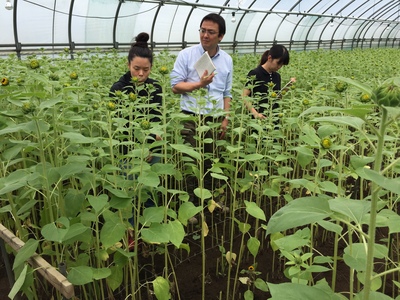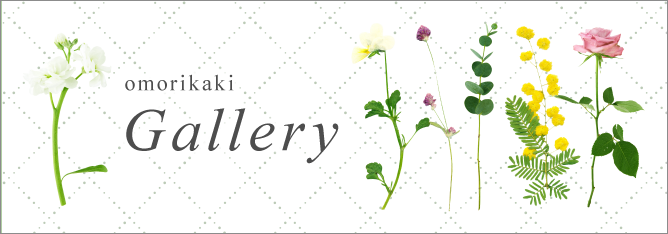もうクリスマスリースはかざりましたか?
毎年恒例のレン先生のレッスンに今年も出席してきました。
今年のテーマカラーは「ピンク&ホワイト&カッパー」
定番は赤&緑&ゴールドですが、毎年流行色はあるみたいで昨年は赤&カッパーでした。
クリスマスツリーもですが、リースやスワッグなどには魔よけの意味があります。西洋でクリスマスは日本で云うお正月みたいなもの。神聖な意味のある常緑樹を玄関に飾ることで、家の中に悪いものをいれない様にするのがはじまり。つまり日本のお正月飾りと全く意味は同じ。文化は違えど人の考える事は昔から国籍を超えて同じなんですね~。
と、いうことで今年のクリスマスリースはこんなのつくりました♪
 今年のリースはいつものリースとはちょっと違う作り方でした。このたびレン先生が考えた新しい作り方。しかも少ない材料で簡単に!がコンセプト!
リース型のオアシスにヒバをワイヤーで巻いたものを板に結束バンドでくっつけて、オアシス部分にモミ、ヒバ、グレビリア(ゴールドパック)の葉、そして白樺の皮をバランスよくオアシス部分にUピンでくっつけてます。ポイントは富士山のように山なりに貼りつけること。これでベースはできあがり。
グレビリアの葉は表はグリーンなんですが、裏がゴールドで裏をみせてもキレイな葉なんです。コチラは輸入のみになりますが、日本にあるものだとタイサンボクみたいなかんじです。
そしたらオーナメント類をUピン、またはグル―でくっつけて完成♪
今年のリースはいつものリースとはちょっと違う作り方でした。このたびレン先生が考えた新しい作り方。しかも少ない材料で簡単に!がコンセプト!
リース型のオアシスにヒバをワイヤーで巻いたものを板に結束バンドでくっつけて、オアシス部分にモミ、ヒバ、グレビリア(ゴールドパック)の葉、そして白樺の皮をバランスよくオアシス部分にUピンでくっつけてます。ポイントは富士山のように山なりに貼りつけること。これでベースはできあがり。
グレビリアの葉は表はグリーンなんですが、裏がゴールドで裏をみせてもキレイな葉なんです。コチラは輸入のみになりますが、日本にあるものだとタイサンボクみたいなかんじです。
そしたらオーナメント類をUピン、またはグル―でくっつけて完成♪
 1か月ちかく外の乾燥した場所に飾るものなので、フレッシュはモミなど枝類くらいそのモミも散りづらいオレゴン産を使用しています。残念ながら、水に付けない場合は日本のモミだとすぐに散ってしまします。
直径50cmくらいの大きなリースですが、見た目に反して材料はとても少ないです。多種少量ってかんじ。
<使用花材>
・一辺が30cm前後の板
・リース型オアシス
・モミ枝×1
・ヒバ2種×各2本
・グレビリアの葉6枚
・ポポラスメタリックピンクの葉×8枚位
・松笠×7個
・コットン×2ヘッド
・ペッパーベリー赤×2本
・モス赤×ちょろっと
・シュガーバインゴールド(フェイク)15cm×2本
・アジサイ白(フェイク)×1かけ
・カッパー色の実(フェイク)×2本
・星とツリーのオーナメント×1個づつ
・リボン15cmくらい
・垂れるきらきらオーナメント×1本
・白の星のオーナメント×7個
ポイントは丸を意識する事。弊社の同僚は四角くなってました(笑)。あとはリースなので真ん中の空洞をちゃんと残すこと。あとはもう自由に飾り付けて、さいごにスノーパウダーとグリッターピンクをふりかけてます。
だれかがつくったキレイなレースを飾るのもいいですが、へたっぴでも自分で作った物には愛着もわきますよ♪いつも自分で作らない方も今年はぜひ挑戦してみて下さいね~
1か月ちかく外の乾燥した場所に飾るものなので、フレッシュはモミなど枝類くらいそのモミも散りづらいオレゴン産を使用しています。残念ながら、水に付けない場合は日本のモミだとすぐに散ってしまします。
直径50cmくらいの大きなリースですが、見た目に反して材料はとても少ないです。多種少量ってかんじ。
<使用花材>
・一辺が30cm前後の板
・リース型オアシス
・モミ枝×1
・ヒバ2種×各2本
・グレビリアの葉6枚
・ポポラスメタリックピンクの葉×8枚位
・松笠×7個
・コットン×2ヘッド
・ペッパーベリー赤×2本
・モス赤×ちょろっと
・シュガーバインゴールド(フェイク)15cm×2本
・アジサイ白(フェイク)×1かけ
・カッパー色の実(フェイク)×2本
・星とツリーのオーナメント×1個づつ
・リボン15cmくらい
・垂れるきらきらオーナメント×1本
・白の星のオーナメント×7個
ポイントは丸を意識する事。弊社の同僚は四角くなってました(笑)。あとはリースなので真ん中の空洞をちゃんと残すこと。あとはもう自由に飾り付けて、さいごにスノーパウダーとグリッターピンクをふりかけてます。
だれかがつくったキレイなレースを飾るのもいいですが、へたっぴでも自分で作った物には愛着もわきますよ♪いつも自分で作らない方も今年はぜひ挑戦してみて下さいね~
 今年のリースはいつものリースとはちょっと違う作り方でした。このたびレン先生が考えた新しい作り方。しかも少ない材料で簡単に!がコンセプト!
リース型のオアシスにヒバをワイヤーで巻いたものを板に結束バンドでくっつけて、オアシス部分にモミ、ヒバ、グレビリア(ゴールドパック)の葉、そして白樺の皮をバランスよくオアシス部分にUピンでくっつけてます。ポイントは富士山のように山なりに貼りつけること。これでベースはできあがり。
グレビリアの葉は表はグリーンなんですが、裏がゴールドで裏をみせてもキレイな葉なんです。コチラは輸入のみになりますが、日本にあるものだとタイサンボクみたいなかんじです。
そしたらオーナメント類をUピン、またはグル―でくっつけて完成♪
今年のリースはいつものリースとはちょっと違う作り方でした。このたびレン先生が考えた新しい作り方。しかも少ない材料で簡単に!がコンセプト!
リース型のオアシスにヒバをワイヤーで巻いたものを板に結束バンドでくっつけて、オアシス部分にモミ、ヒバ、グレビリア(ゴールドパック)の葉、そして白樺の皮をバランスよくオアシス部分にUピンでくっつけてます。ポイントは富士山のように山なりに貼りつけること。これでベースはできあがり。
グレビリアの葉は表はグリーンなんですが、裏がゴールドで裏をみせてもキレイな葉なんです。コチラは輸入のみになりますが、日本にあるものだとタイサンボクみたいなかんじです。
そしたらオーナメント類をUピン、またはグル―でくっつけて完成♪
 1か月ちかく外の乾燥した場所に飾るものなので、フレッシュはモミなど枝類くらいそのモミも散りづらいオレゴン産を使用しています。残念ながら、水に付けない場合は日本のモミだとすぐに散ってしまします。
直径50cmくらいの大きなリースですが、見た目に反して材料はとても少ないです。多種少量ってかんじ。
<使用花材>
・一辺が30cm前後の板
・リース型オアシス
・モミ枝×1
・ヒバ2種×各2本
・グレビリアの葉6枚
・ポポラスメタリックピンクの葉×8枚位
・松笠×7個
・コットン×2ヘッド
・ペッパーベリー赤×2本
・モス赤×ちょろっと
・シュガーバインゴールド(フェイク)15cm×2本
・アジサイ白(フェイク)×1かけ
・カッパー色の実(フェイク)×2本
・星とツリーのオーナメント×1個づつ
・リボン15cmくらい
・垂れるきらきらオーナメント×1本
・白の星のオーナメント×7個
ポイントは丸を意識する事。弊社の同僚は四角くなってました(笑)。あとはリースなので真ん中の空洞をちゃんと残すこと。あとはもう自由に飾り付けて、さいごにスノーパウダーとグリッターピンクをふりかけてます。
だれかがつくったキレイなレースを飾るのもいいですが、へたっぴでも自分で作った物には愛着もわきますよ♪いつも自分で作らない方も今年はぜひ挑戦してみて下さいね~
1か月ちかく外の乾燥した場所に飾るものなので、フレッシュはモミなど枝類くらいそのモミも散りづらいオレゴン産を使用しています。残念ながら、水に付けない場合は日本のモミだとすぐに散ってしまします。
直径50cmくらいの大きなリースですが、見た目に反して材料はとても少ないです。多種少量ってかんじ。
<使用花材>
・一辺が30cm前後の板
・リース型オアシス
・モミ枝×1
・ヒバ2種×各2本
・グレビリアの葉6枚
・ポポラスメタリックピンクの葉×8枚位
・松笠×7個
・コットン×2ヘッド
・ペッパーベリー赤×2本
・モス赤×ちょろっと
・シュガーバインゴールド(フェイク)15cm×2本
・アジサイ白(フェイク)×1かけ
・カッパー色の実(フェイク)×2本
・星とツリーのオーナメント×1個づつ
・リボン15cmくらい
・垂れるきらきらオーナメント×1本
・白の星のオーナメント×7個
ポイントは丸を意識する事。弊社の同僚は四角くなってました(笑)。あとはリースなので真ん中の空洞をちゃんと残すこと。あとはもう自由に飾り付けて、さいごにスノーパウダーとグリッターピンクをふりかけてます。
だれかがつくったキレイなレースを飾るのもいいですが、へたっぴでも自分で作った物には愛着もわきますよ♪いつも自分で作らない方も今年はぜひ挑戦してみて下さいね~